1. インデックスとは?
インデックス(index)とは、データ構造の要素にアクセスするための「位置番号」のことです。
 ITTI
ITTIたとえば、先生が『出席番号順に答えて』と言うと、生徒が『1番!』『2番!』と順番に答えますよね。この番号がインデックスのイメージです。
この「順番に並んだ番号」が、まさにインデックスのイメージです。
JavaScriptでは主に以下の場面で登場します。
• 配列(Array):要素の順序を示す番号
• 文字列(String):文字の位置を示す番号
• オブジェクトやMap:キーをインデックス的に扱うケース
• ループ処理:forやforEachでインデックスを利用
などなど



インデックスがあるおかげで、1つの配列の中に複数のデータをまとめて管理できます。
もしインデックスがなければ、配列の中で、fruit1, fruit2, fruit3 のように変数をたくさん作る必要があり、コードが煩雑になります。
インデックスを使えば、fruits[0] や fruits[1] のように1つの配列から自由に要素を選べるため、コードをシンプルに保てるのです。



ということで、ここからはコード専門官のイティセルが解説します。イティセルさん!よろしくお願いします!



イティセルです。読者の皆さんにわかりやすくお伝えしていきますね!
2. 配列とインデックス
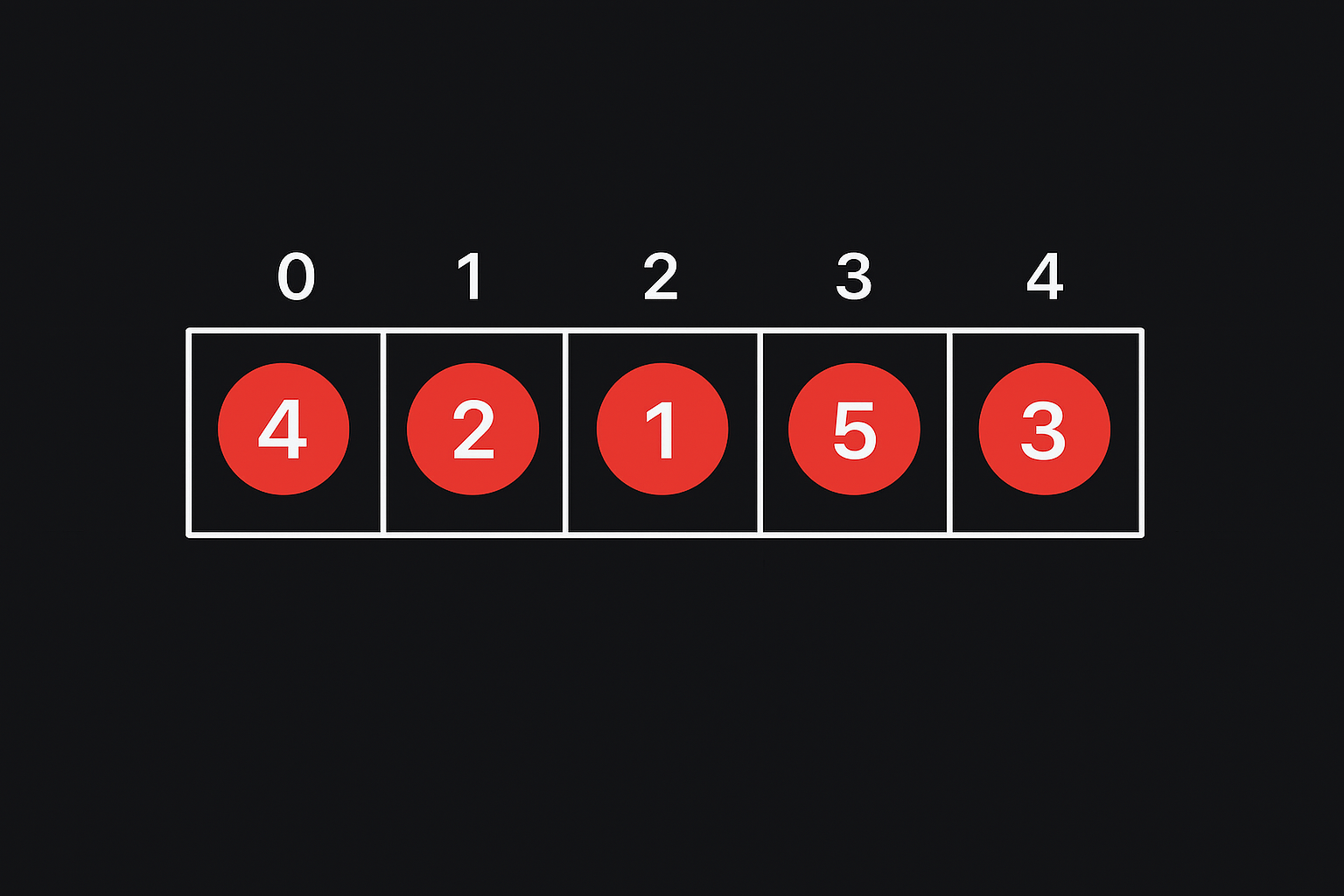
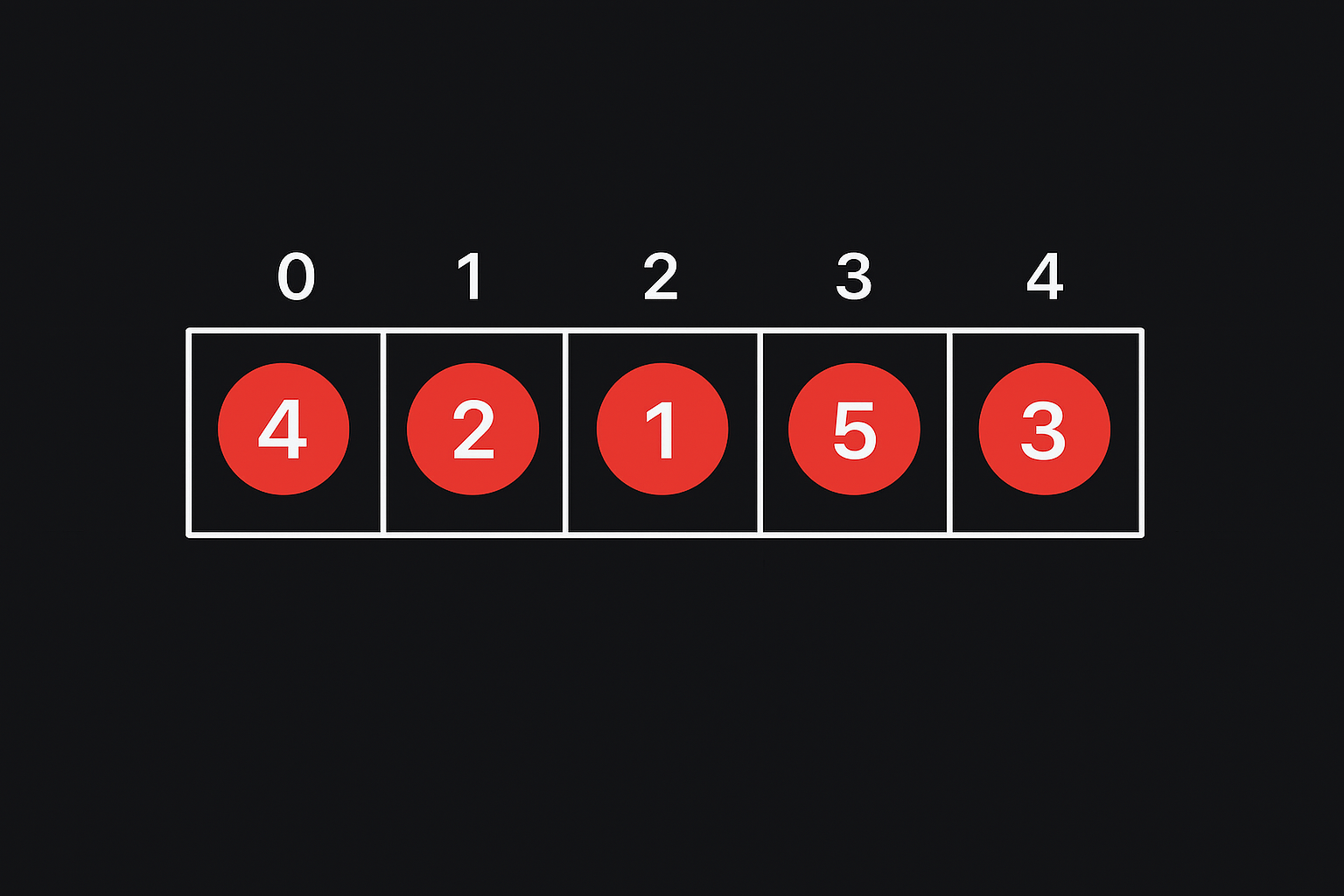
配列は最も典型的にインデックスを使うデータ構造です。
JavaScriptの配列は0から始まるインデックスを持ちます。



appleを選びたいから、0番を指定しよう
const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];
console.log(fruits[0]);
実行結果
"apple"


cherryを選びたいから、2番を指定しよう
const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];
console.log(fruits[2]);
実行結果
"cherry"2.1 インデックスを使った要素の更新



1番目にあるbananaからorangeに更新しよう
const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];
fruits[1] = "orange";
console.log(fruits);
実行結果
["apple", "orange"(⇦更新してる!) , "cherry"]2.2 配列の長さとインデックス
array.lengthは要素数を返します。JavaScriptの配列はインデックスが 0から始まる ため、最後の要素を取得するには「要素数 – 1」を指定する必要があります。



例えば、次の配列には “apple”, “banana”, “cherry” の3つの要素があります。
要素数は3つなので、最後の要素を取り出すには 3 – 1 = 2、つまり2番を指定します。
const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];
console.log(fruits[fruits.length - 1]);
実行結果
"cherry"3. 文字列とインデックス


文字列も配列のようにインデックスでアクセス可能です。



インデックスは 0から始まる ので、最初の文字は 0 を指定します。
const word = "JavaScript";
console.log(word[0]);
実行結果
"J"


文字列の最後の文字を取り出すには、length – 1 を指定します。
“JavaScript” は 10文字なので、10 – 1 = 9=9番目を指定すると “t” が取り出せます。
const word = "JavaScript";
console.log(word[word.length - 1]);
実行結果
"t"
ただし、文字列はイミュータブル(変更不可)なので、word[0] = “X” のような代入はできません。



イミュータブル(immutable)とは「変更できない」という意味です。
JavaScriptにおいて、文字列はイミュータブルなデータ型に分類されます。つまり、一度作られた文字列は、その中身を直接書き換えることができません。
例えば「JavaScript」という文字列があったとします。この文字列の先頭を「X」に変えて「XavaScript」にしようとしても、元の文字列を直接改造することはできません。文字列は常に固定されており、部分的に差し替えることは不可能なのです。
let word = "JavaScript";
word[0] = "X"; ⇦注目!!!!!JをXに変更しようとしてる
console.log(word);
実行結果
"JavaScript"(変わらない)


文字列を変更したい場合は、新しい文字列を作り直す必要があります。
let word = "JavaScript";
word = "X" + word.slice(1); →XとavaScriptを合わせよっていう命令に設定
console.log(word);
実行結果
"XavaScript"4. インデックス検索メソッド
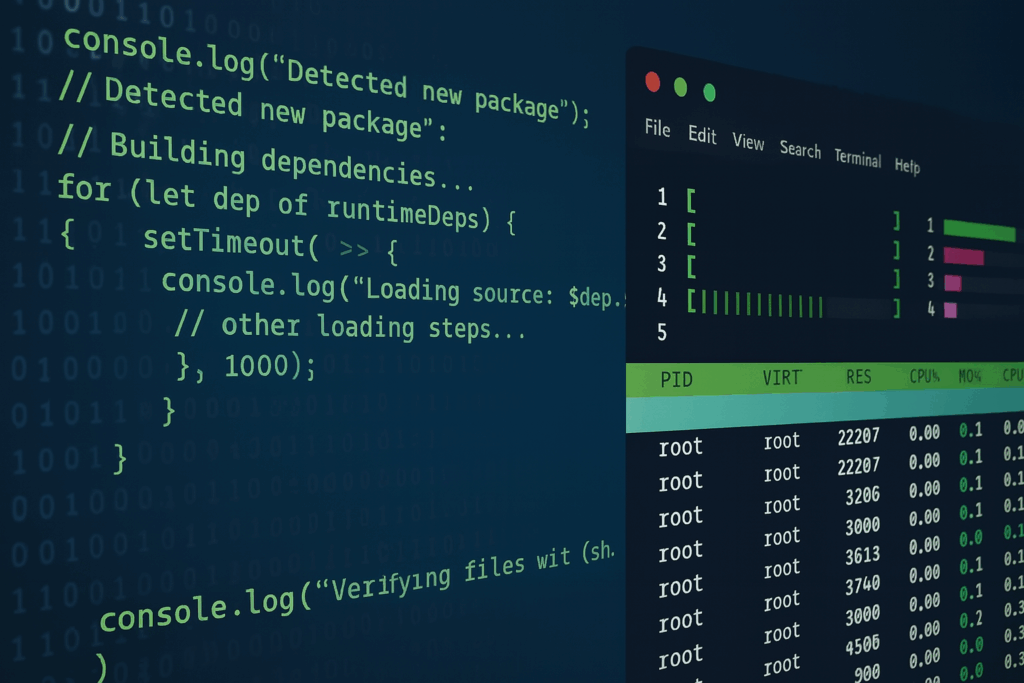
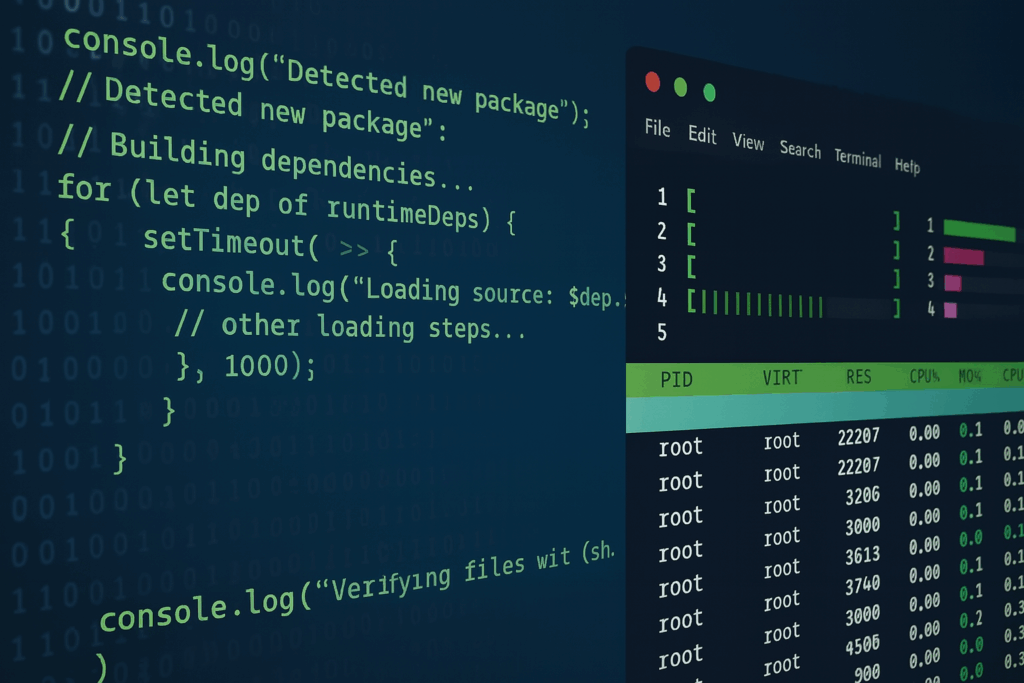
4.1 `indexOf` と `lastIndexOf`
const colors = ["red", "blue", "green", "blue"];
console.log(colors.indexOf("blue"));
実行結果
1


最初に出てくる “blue” は 1番 にあったね
const colors = ["red", "blue", "green", "blue"];
console.log(colors.lastIndexOf("blue"));
実行結果
3


最後に出てくる “blue” は 3番 にあったね
4.2 `findIndex`



25より大きい数字は何番かな?
const numbers = [10, 20, 30, 40];
const index = numbers.findIndex(n => n > 25);
console.log(index);
実行結果
2


25より大きい数字は30で、結果は2番だね
5. ループとインデックス
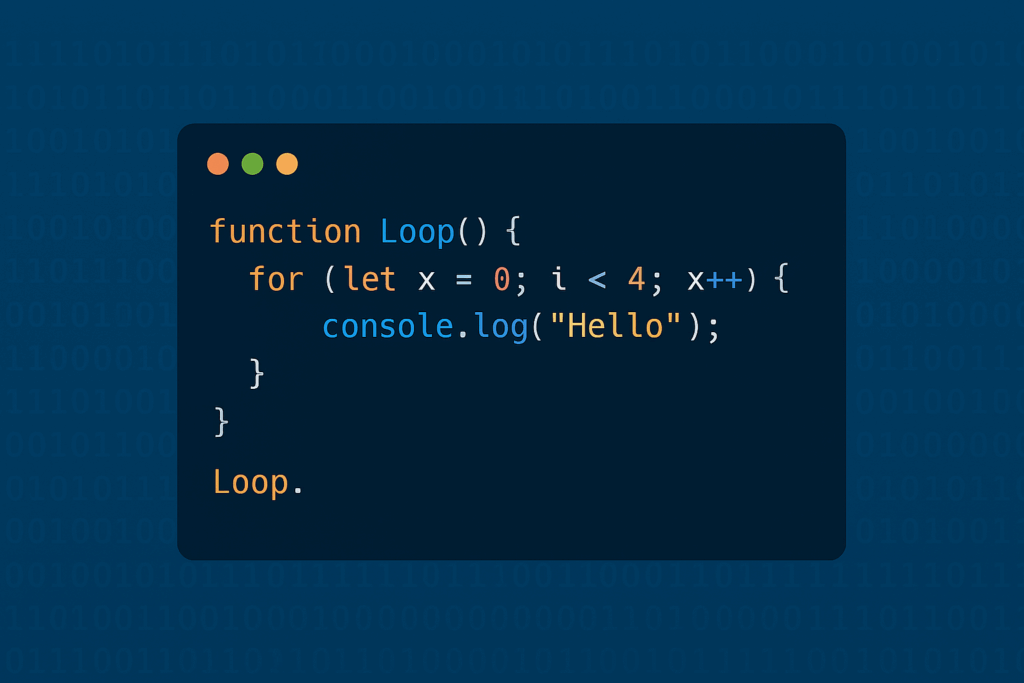
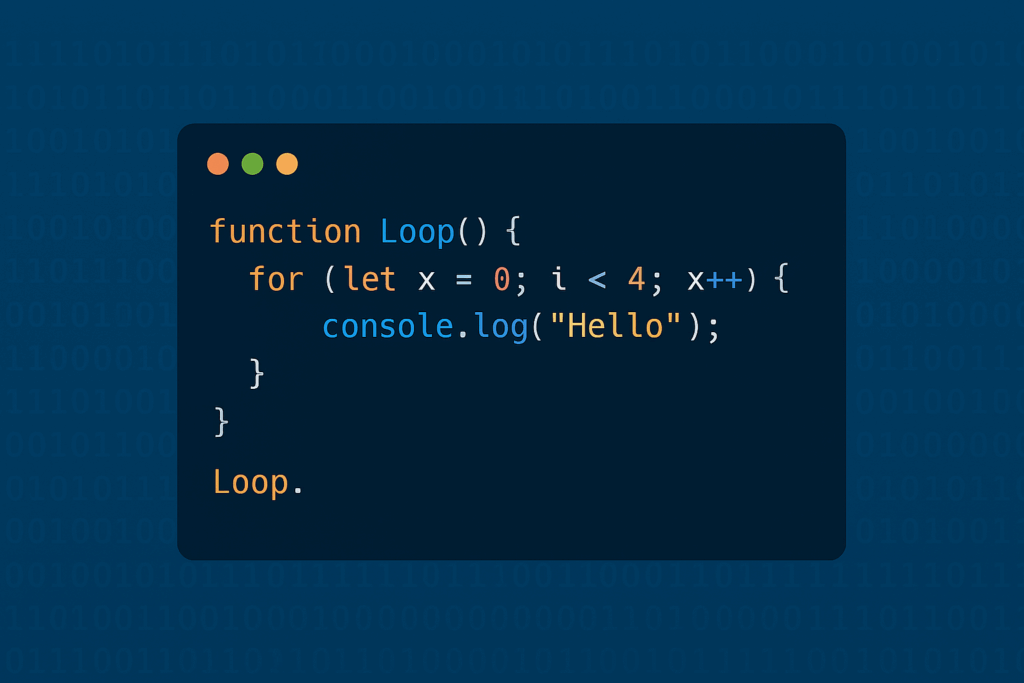
5.1 `for`ループ



forを使ってループさせてみよう
const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];
for (let i = 0; i < fruits.length; i++) {
console.log(i, fruits[i]);
}
実行結果
0 apple
1 banana
2 cherry


実行結果は 0 → 1 → 2 と順番に並んでいますね。
for ループは インデックスを一度ずつ進めていくだけで、0に戻って繰り返すわけではありません。
5.2 `forEach`



forEachを使ってループさせてみよう
const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];
fruits.forEach((item, index) => {
console.log(index, item);
});
実行結果
0 apple
1 banana
2 cherry


forEach は配列の要素を順番に処理するメソッドです。
for のコードと比べると、シンプルで読みやすいのが特徴です。
ただし、forEach では break や continue が使えない点には注意しましょう。
6. オブジェクトとインデックス的アクセス
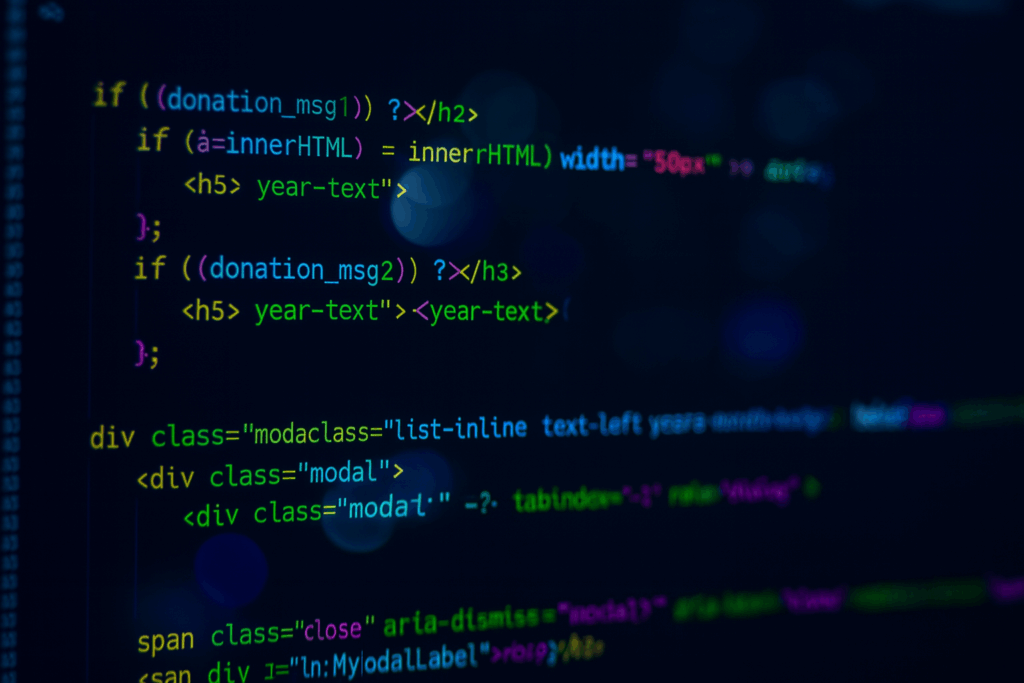
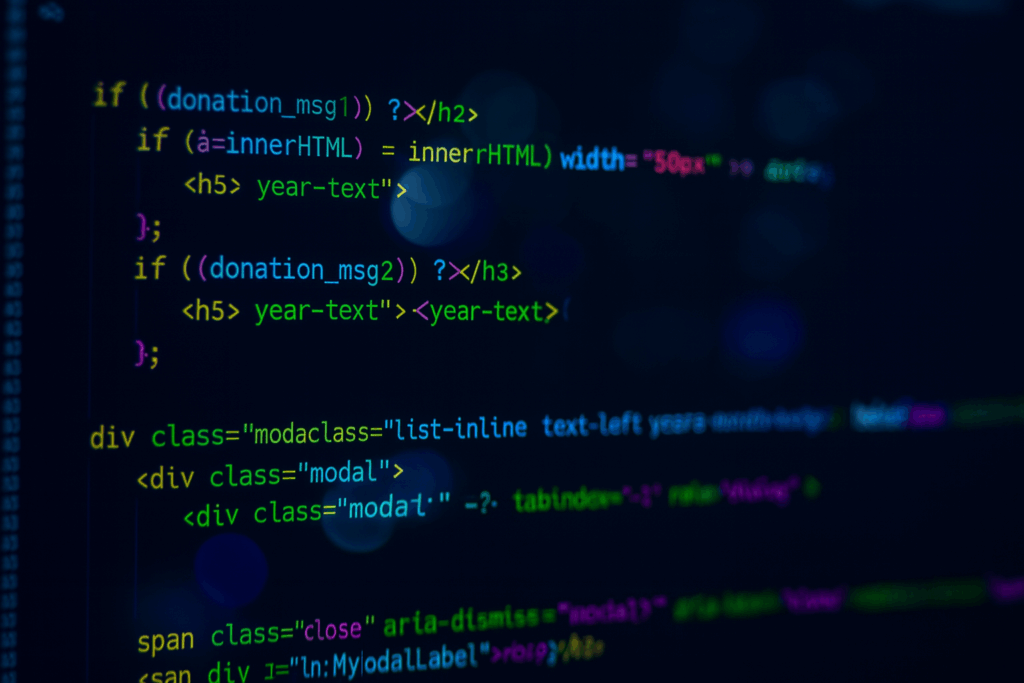
オブジェクトは数値インデックスを持ちませんが、キーをインデックス的に扱うことができます。



まず、キーは “name”, “age”, “city”とします。
Object.keys() を使えばキーを配列として取り出し、インデックス的に扱うことができます。
const user = { name: "Taro", age: 25, city: "Tokyo" };
const keys = Object.keys(user);
console.log(keys[0]);
実行結果
"name"


keys[0] は “name” です。つまり「最初のキー」を取り出していますね。



次、
console.log(user[keys[0]]); の中で書かれている user は「オブジェクトの名前」です。
keys[0] は “name” なので、user[keys[0]] は user[“name”] と同じ意味になります。
つまり「キー “name” に対応する値を取り出す」ということになり、実行結果は “Taro” です。
わかりやすくすると
• keys[0] は “name”
• user[“name”] → “Taro”
となり、結果は”Taro”になるわけです。
const user = { name: "Taro", age: 25, city: "Tokyo" };
const keys = Object.keys(user);
console.log(user[keys[0]]);
実行結果
"Taro"7. Map/Setとインデックス


MapやSetは順序を保持しますが、直接インデックスでアクセスはできません。(map.keys()[1] はエラー)
代わりにイテレーションで順序を利用します。
その前に 配列の map() メソッド について説明します!



map() とは、配列の全ての要素に処理をかけて、新しい配列を作るメソッドです。
const numbers = [1, 2, 3];
const doubled = numbers.map(n => n * 2);
console.log(doubled);
実行結果
[2, 4, 6]


このコードでは、配列 [1, 2, 3] の 全ての要素に ×2 の処理をかけて、
新しい配列 [2, 4, 6] が返されています。
話に戻ります



map.keys() だけでは配列にはなりません。
スプレッド構文 … を使って […map.keys()] と書くことで、イテレーターを配列に変換できます。
その結果 [1] でアクセスでき、実行結果は “name” になります。
もし配列に変換しなければ、インデックスアクセスはできないためエラーになります。
const map = new Map([
["id", 1],
["name", "Hanako"],
["age", 30]
]);
console.log([...map.keys()][1]);
実行結果
"name"const map = new Map([
["id", 1],
["name", "Hanako"],
["age", 30]
]);
console.log(map.keys()[1]);
実行結果
エラー8. 実用例:検索フォームでのインデックス利用


例えば、検索結果リストから「最初に条件を満たす要素の位置」を取得するケース。



要するに、調べたいときに使えるコードです。
indexOf() メソッドを使ってみましょう。
このコードでは、target に “Smartphone” を設定し、配列 products の中から探しています。
products.indexOf(target) は配列の中から “Smartphone” を探し、最初に見つかった位置(インデックス番号)を返します。
const products = ["PC", "Tablet", "Smartphone", "Camera"];
const target = "Smartphone";
const index = products.indexOf(target);


indexOf() は見つからなければ -1 を返す仕様なので、index !== -1 で「見つかったかどうか」を判定しています。
if (index !== -1) {
console.log(`${target} は ${index} 番目にあります`);
}


この例では “Smartphone” が2番目にあるため、実行結果は “Smartphone は 2 番目にあります” と表示されます。
見つからなければ -1 になります。
実行結果
Smartphone は 2 番目にあります9. 配列操作メソッド
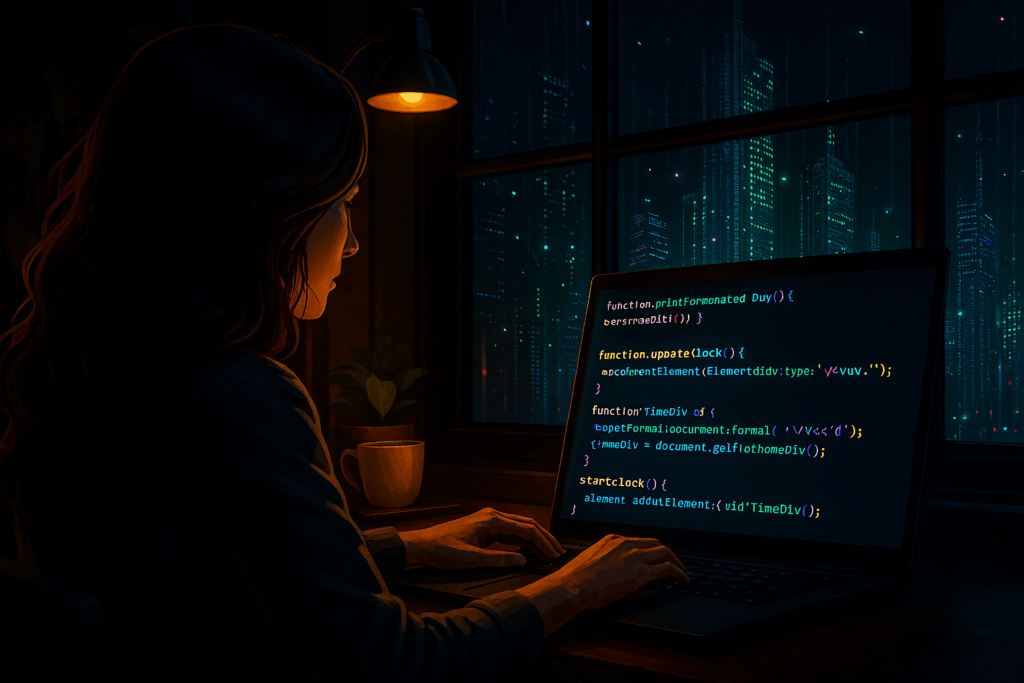
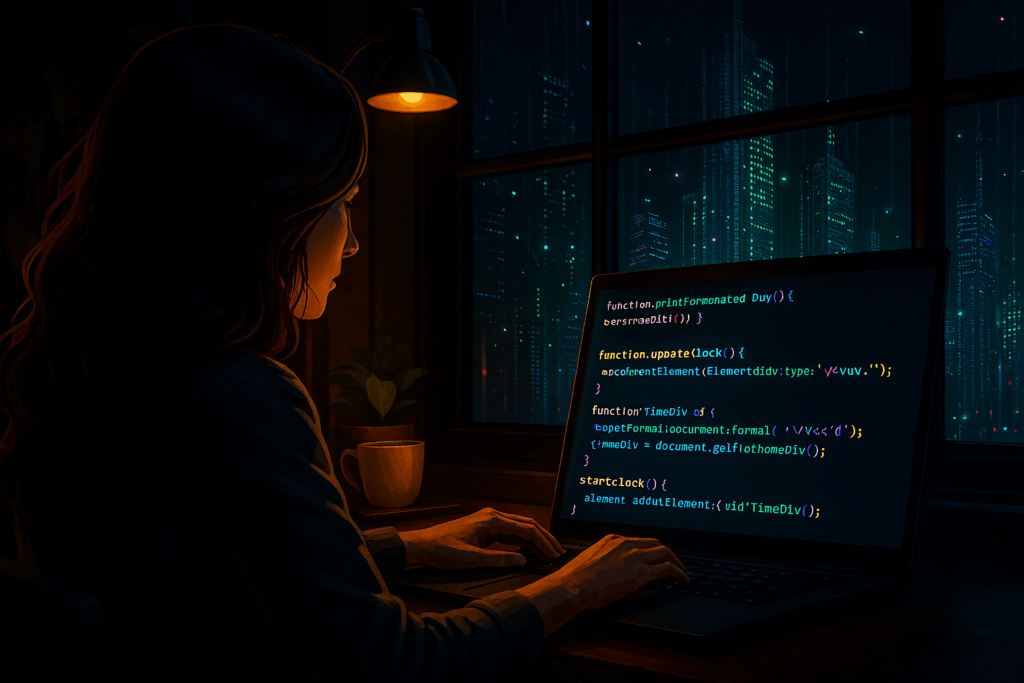
9.1. `push` / `pop` / `shift` / `unshift`



push は配列の末尾に要素を追加します。
例: [1, 2, 3] に 4 を追加すると → [1, 2, 3, 4]
let arr = [1, 2, 3];
arr.push(4);
実行結果
[1, 2, 3, 4]


pop は配列の末尾の要素を削除します。
例: [1, 2, 3, 4] から末尾を削除すると → [1, 2, 3]
let arr = [1, 2, 3, 4];
arr.pop();
実行結果
[1, 2, 3]


shift は配列の先頭の要素を削除します。
例: [1, 2, 3] から先頭を削除すると → [2, 3]
let arr = [1, 2, 3];
arr.shift();
実行結果
[2, 3]


unshift は配列の先頭に要素を追加します。
例: [2, 3] の先頭に 0 を追加すると → [0, 2, 3]
let arr = [2, 3];
arr.unshift(0);
実行結果
[0, 2, 3]9.2 `splice` / `slice`



開始位置:どのインデックスから処理を始めるか
削除する数:そこからいくつ削除するか
追加する要素:削除した場所に挿入する要素
array.splice(開始位置, 削除する数, 追加する要素1, 追加する要素2, ...)


1 → index1(つまり「2」の位置)から始める
2 → そこから2つ削除(「2」と「3」が消える)
99 → その場所に 99 を挿入
let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.splice(1, 2, 99);


arr.splice(1, 2, 99) の動きを説明します。
まず、let arr = [1, 2, 3, 4, 5]; という配列があります。
• インデックス1 は要素「2」の位置を指します。したがって処理の対象は「2, 3, 4, 5」であり、先頭の「1」は対象外です。
• 2 は「そこから2つ削除する」という意味なので、「2」と「3」が削除されます。
• 99 は削除した場所に挿入する要素です。つまり「2」と「3」を削除した位置に「99」が入ります。
その結果、配列は次のように変わります。
実行結果
[1, 99, 4, 5]


1 → index1(要素「20」)から始める
3 → index3(要素「40」)の直前までで止める
つまり、index1 と index2の要素だけがコピーされる → [20, 30]
let arr2 = [10, 20, 30, 40];
let sliced = arr2.slice(1, 3);
console.log(sliced);


わかりやすく言うと、slice(1, 3) は 20から始めて、40の直前で止まります。
そのため対象になるのは「20」と「30」で、「40」は含まれません。
よって実行結果は [20, 30] になります。
実行結果
[20, 30]9.3 `concat` / スプレッド構文 `…`



要するに、concat は配列と配列を組み合わせて新しい配列を返すメソッドです。
a は [1, 2]、b は [3, 4]
a.concat(b) によって a と b が結合され、新しい配列 c が作られる。
console.log(c) を実行すると [1, 2, 3, 4] が表示される。
let a = [1, 2];
let b = [3, 4];
let c = a.concat(b);
console.log(c);
実行結果
[1, 2, 3, 4]


…a は「配列 a の中身を展開する」という意味です。
[…a, …b] と書くと、一見すると配列を組み合わせているように見えますが、実際には a の要素の後に b の要素を並べているだけ です。つまり「a の隣に b を置く」イメージです。
let a = [1, 2];
let b = [3, 4];
let d = [...a, ...b];
console.log(d);
実行結果
[1, 2, 3, 4]10. 検索・判定メソッド
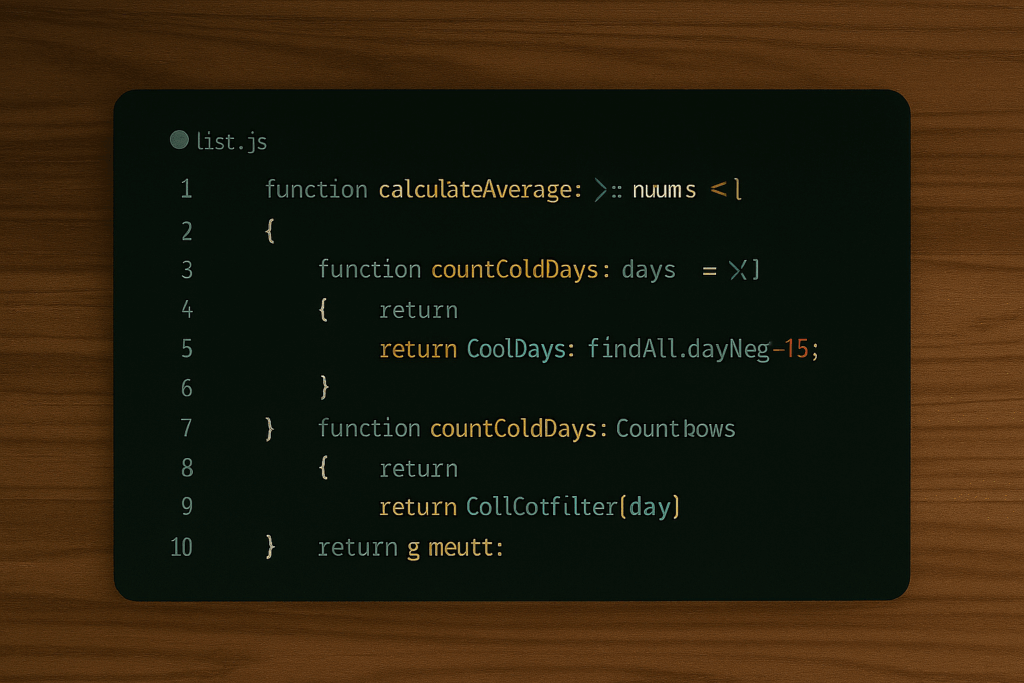
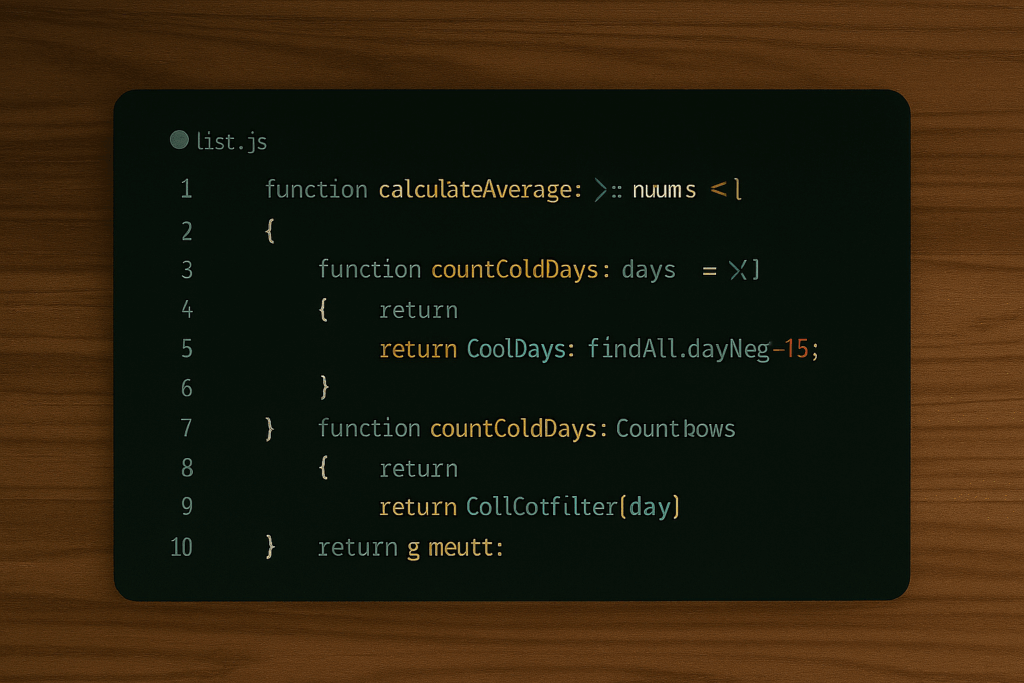
10.1 `includes`



fruits の配列には [“apple”, “banana”, “orange”] が入っています。
console.log(fruits.includes(“banana”)); は、この配列の中に “banana” が含まれているかどうかを調べます。
結果として “banana” は配列に含まれているので、true が返されます。
let fruits = ["apple", "banana", "orange"];
console.log(fruits.includes("banana"));
実行結果
true


このコードは、fruits の中に “grape” が含まれているかどうかを調べます。
しかし、fruits には “grape” が含まれていないため、結果は false になります。
let fruits = ["apple", "banana", "orange"];
console.log(fruits.includes("grape"));
実行結果
false10.2 `some` / `every`



つまり、1つでも条件を満たせば true、1つも満たさなければ false になります。
n > 4 は「4より大きい数字があるかどうか」を調べています。
numbers の中では 5 が 4 より大きいため、結果は true になります。
let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log(numbers.some(n => n > 4));
実行結果
true


つまり、すべての要素が条件を満たせば true、1つでも満たさなければ false になります。
n > 0 は「0より大きい数字かどうか」を調べています。
numbers の中のすべての要素が 0 より大きいため、結果は true になります。
let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log(numbers.every(n => n > 0));
実行結果
true11. 反復処理と変換


11.1 `filter`



要するに、次のコードを見ると「2で割り切れる数字(偶数)」だけが抽出されているのがわかります。つまり、条件を満たす要素だけを取り出すということです。
nums には 1 から 5 までの数字が入っています。
nums.filter(n => n % 2 === 0);
このコードは、nums の中から「2で割ったときに余りが出ない数字」を抽出します。実行すると、条件を満たす数値は [2, 4] だとわかります。
let nums = [1, 2, 3, 4, 5];
let evens = nums.filter(n => n % 2 === 0);
実行結果
[2, 4]


ここで出てくる n は、配列の要素を一つずつ受け取る仮の変数名です。慣習的に number の略として n がよく使われますが、決まりはなく、num や value など自由に名前を変えることができます。
要するに、ここでの n は配列の要素を順番に受け取るための仮の名前です。
このように仮の変数を使うことで、配列の要素を一つずつ処理するコードをシンプルに短く書けるように設計されています。
もし n のような仮の変数を使わなければ、同じ処理をするのにもっと長いコードを書かなくてはなりません。
11.2 `reduce`



nums に [1, 2, 3, 4] があるとします。
reduce を使うと、すべての要素を合計して結果は 10 になります。
let nums = [1, 2, 3, 4];
let sum = nums.reduce((acc, cur) => acc + cur, 0);
実行結果
10


acc は「これまでの計算結果」
cur は「現在の要素」
初期値 0 から始めて、順番に足し合わせていく
acc と cur という名前は決まりではありません。自由に名前をつけられますが、慣習的にこの書き方がよく使われます。



簡単にいうと、
[1, 2, 3, 4] の場合、「1 を計算し終えたから次は 2」「2 を足したから次は 3」というように、acc に途中結果が入り、cur が [1, 2, 3, 4]を順番に処理されていきます。
1. 初期値 0 が acc に入る
◦ cur = 1 → acc + cur = 0 + 1 = 1
2. 次の要素
◦ acc = 1, cur = 2 → 1 + 2 = 3
3. 次の要素
◦ acc = 3, cur = 3 → 3 + 3 = 6
4. 次の要素
◦ acc = 6, cur = 4 → 6 + 4 = 10


最終的に acc が 10 になり、それが reduce の戻り値になります。
12. 配列の並び替え


12.1 `sort`



sort() は 要素を文字列に変換して、文字コード(辞書順)で比べるんです。
• “10” → 先頭が “1”
• “2” → 先頭が “2”
• “30” → 先頭が “3”
この「先頭の文字」を比べるので、
“1” → “2” → “3” の順番になり、結果が [10, 2, 30] になるんです。
let nums = [10, 2, 30];
nums.sort();
console.log(nums);
[10, 2, 30]


(a, b) => a – b を渡したときの sort は、「小さい数から順番に並べる(昇順)」 という動きをします。
裏側では「a – b が負なら a が先、正なら b が先」というルールで比較してるんですが、実際に使うときは「小さい順に並ぶ」と覚えておけば十分です。
let nums = [10, 2, 30];
nums.sort((a, b) => a - b);
console.log(nums);
[2, 10, 30]12.2 `reverse`



reverse を使うと、配列の要素を逆の順番に並べ替えます。
let arr = [1, 2, 3];
arr.reverse();
[3, 2, 1]13.オブジェクト配列の操作



次のような users 配列があります。
let users = [
{ id: 1, name: "Taro" },
{ id: 2, name: "Hanako" },
{ id: 3, name: "Ken" }
];


users.find(u => u.id === 2); は、id が 2 の要素を探す という意味です。
let user = users.find(u => u.id === 2);
console.log(user);


users の中から 2 の要素が見つかったので、実行結果は { id: 2, name: “Hanako” } になります。
実行結果
{ id: 2, name: "Hanako" }14. 応用テーマ
多次元配列



配列の中にさらに配列を入れることができます。これを 多次元配列 と呼びます。
let matrix = [
[1, 2],
[3, 4],
[5, 6]
];


さらに、二重のインデックスでアクセスできます。
matrix[1] → [3, 4]
その [0] → 3
matrix[1] はインデックス 1 の要素なので [3, 4] です。
さらにその [0] を指定すると、[3, 4] の先頭要素である 3 が取り出せます。
したがって実行結果は 3 になります。
console.log(matrix[1][0]);
実行結果
3まとめ
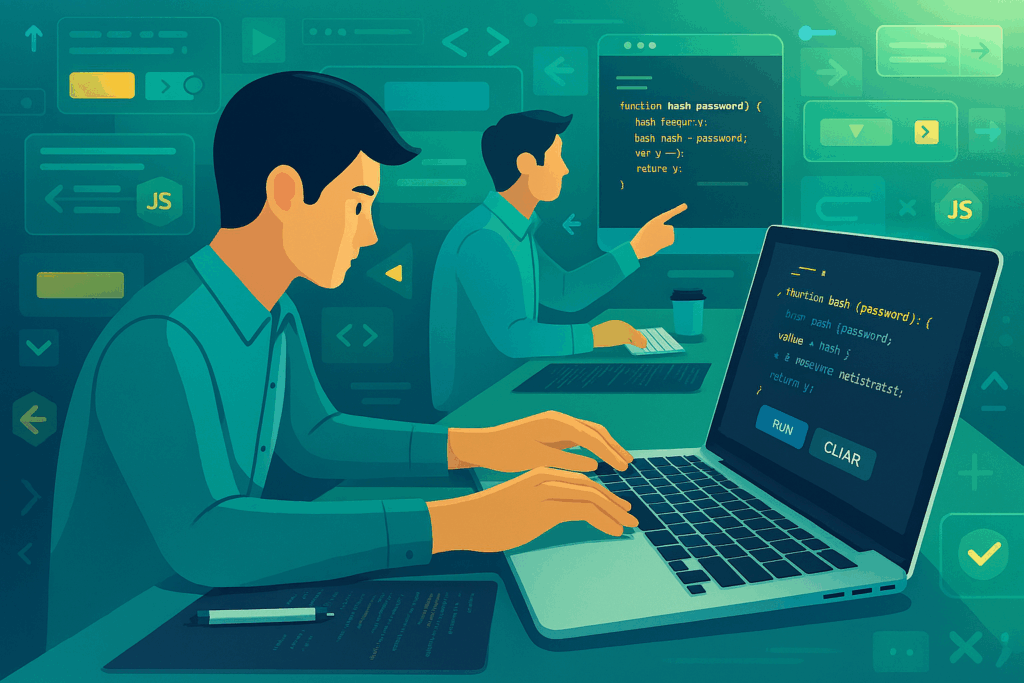
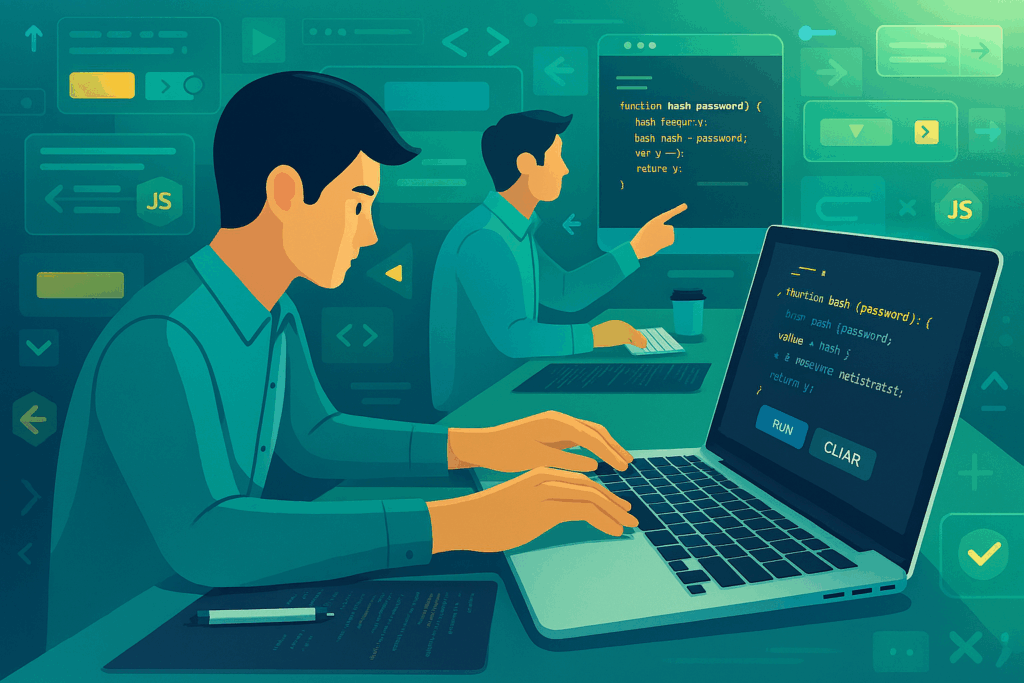
インデックス(index)とは、配列や文字列などの要素にアクセスするための「位置番号」です。
JavaScript では 0から始まる ことが大きな特徴で、データ操作の基盤となる考え方です。
本記事では、以下の観点からインデックスを解説しました。
復習してみましょう!
1. 基本概念
• 人間は 1 から数えるが、JavaScript のインデックスは 0 から始まる
• 配列や文字列の要素にアクセスする際に使う
• インデックスがあることで、複数のデータを効率的に管理できる



インデックスがなければ、配列の中の要素を扱うたびに fruit1, fruit2, fruit3… のように個別の変数を用意しなければならず、コードは長くなり紛らわしいものでした。
そこで インデックスという仕組みが導入され、配列や文字列を「位置番号」で扱えるようになったのです。
このおかげでコードは短く、読みやすくなり、JavaScriptを使う人にとっても大きな利便性をもたらしました。
2. 配列とインデックス
• fruits[0] → “apple” のように要素を取り出せる
• fruits[1] = “orange” のように更新も可能
• array.length – 1 で最後の要素にアクセスできる



fruits を使えば、インデックス番号で要素を取り出すことができます。
また、配列の最後の要素を取り出したい場合は array.length – 1 を指定します。
こうした基本を覚えておくと、コードをシンプルかつ効率的に書けるようになります。
3. 文字列とインデックス
• “JavaScript”[0] → “J”
• “JavaScript”[word.length – 1] → “t”
• 文字列はイミュータブルなので直接変更はできず、新しい文字列を作り直す必要がある



イミュータブル(変更できない)については以前も説明しましたが、もし忘れていたらここで思い出してください。
つまり、文字列の中身を直接書き換えることはできず、新しい文字列を作り直す必要があります。
4. インデックス検索メソッド
• indexOf / lastIndexOf → 要素の位置を検索
• findIndex → 条件に合う最初の要素の位置を返す



配列の中に要素がたくさんある場合、indexOf や lastIndexOf を使えば、特定の要素がどの位置にあるかを簡単に調べられます。
また、findIndex を使えば「条件に合う最初の要素の位置」を取得できます。
これらのメソッドを活用することで、検索処理をシンプルに書けるのが便利なポイントです。
5. ループとインデックス
• forループで i を使って順番に処理
• forEachで (item, index) を受け取り、シンプルに書ける



柔軟に制御したいならfor。シンプルに書きたいならforEach。
6. オブジェクトとインデックス的アクセス
• Object.keys(obj)でキーを配列化し、インデックスでアクセス可能
• user[keys[0]]のように「キーを経由して値を取り出す」ことができる



Object.keys(obj) は、オブジェクトのキーを配列としてまとめて取り出せます。
そして user[keys[0]] のように書くと、そのキーに対応する値を取り出すことができます。
7. Map / Set とインデックス
• map.keys()はイテレーターで、そのままではインデックスアクセス不可
• […map.keys()]とスプレッド構文で配列化すれば要素の[1]のようにアクセスできる
• Setも順序を保持するが、直接インデックス指定はできない



インデックスアクセスをしたい場合は、map.keys()のままではできません。
スプレッド構文を使って […map.keys()] のように配列化すれば、要素の[1]のようにインデックス指定で要素を取り出せるようになります。
8. 配列操作メソッドとインデックス
• push / pop / shift / unshift → 先頭・末尾の追加削除
• splice / slice → 部分的な削除・コピー
• concat / スプレッド構文 … → 配列の結合



これらのメソッドを上手く使えると、配列を自在に操作できるようになり、より高度なコードを書けるようになります。
イメージしやすいようにゲームに例えると:
• push:ゾンビが次々と現れる → 配列の末尾に追加
• pop:倒した敵を消す → 配列の末尾を削除
• shift:先頭のキャラが退場する → 配列の先頭を削除
• unshift:新しい仲間が先頭に加わる → 配列の先頭に追加
• splice:敵を途中からまとめて消す、または差し替える → 部分的に削除・置換
• slice:ステージの一部だけ切り出す → 部分配列をコピー
9. 検索・判定
• includes → 要素が含まれているかを真偽値で返す
• some / every → 条件を満たす要素があるか/すべて満たすか



人狼ゲームに例えるとわかりやすいです。
includes:占い師が生存者リストを調べて、人狼が含まれているかを確認する。
some:プレイヤーの中に「人狼が1人でもいるか」を判定する。
every:全員が市民かどうかを確認する。
10. 反復処理と変換
• filter → 条件に合う要素だけを抽出
• map → 要素を変換して新しい配列を作成
• reduce → 配列全体を 1 つの値に集約



例えば、filter を使えば「大卒の人だけ」を抽出できます。
map を使えば「学歴の一覧」だけを新しい配列として作れます。
さらに reduce を使えば「全員の年齢を合計する」といった集約処理ができます。
11. 並び替えと反転
• sort → デフォルトは文字列比較、数値は比較関数を指定
• reverse → 配列を逆順に並べ替える



reverse を使うと、配列の順番をひっくり返せます。
例えば「ゾンビから人間に復活する」ように状態を逆転させたり、「古いPCから新しいPCへ」と順序を逆にするイメージです。
sort を使うと、配列を並び替えられます。
例えば「年齢順に並べる」「名前をアルファベット順に並べる」といった使い方ができます。
12. 応用テーマ
• オブジェクト配列:findで条件検索
• 多次元配列:matrix[1][0] のように二重のインデックスでアクセス



多次元配列では、matrix[1][0]のようにインデックスを二重に指定してアクセスします。
「二重インデックス=2回行動」と考えると、イメージしやすく覚えやすいでしょう。
インデックスを理解する意義
インデックスを正しく理解すれば、
• 配列や文字列の操作が直感的にできる
• 検索や更新処理を効率的に書ける
• オブジェクトや Map/Set、多次元配列など幅広いデータ構造を自在に扱える
つまり、インデックスは JavaScriptのデータ操作を支える基礎概念です。



ぜひ実際に手を動かして試してくださいね、頑張ってくださいね!
この記事が参考になったと感じたら、ぜひシェアやコメントで教えてください。
今後の改善に役立てます。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
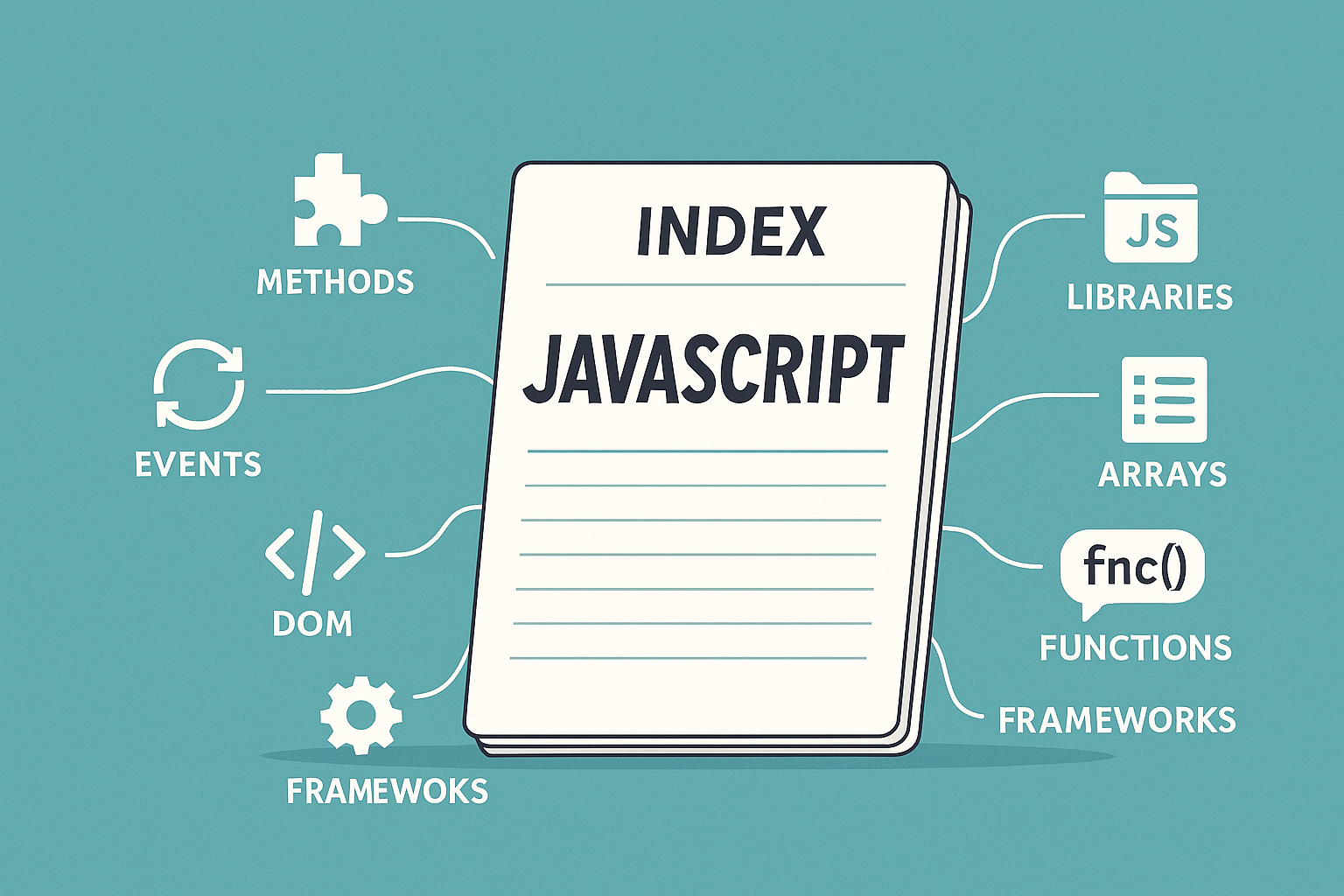

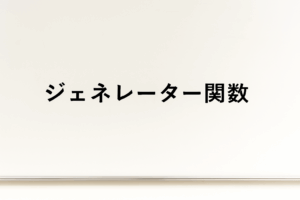

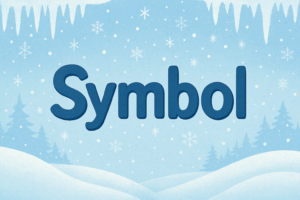


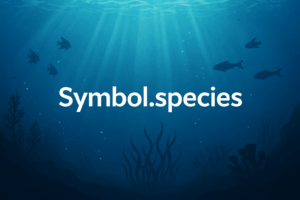
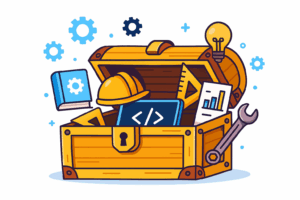

コメント